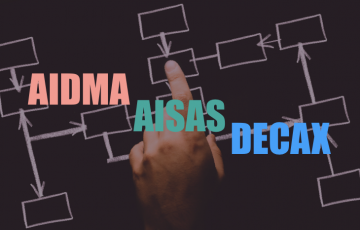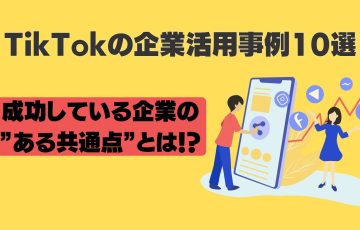目次
マーケティングアジェンダ2018
梅雨入りが発表された沖縄県読谷村で行われた、日本のトップマーケター約400人が参加した一大イベント「マーケティングアジェンダ2018」。
最近話題のP&Gマフィア(※)を始め、多数のCMOクラスの方々、一流代理店やプラットフォーマーも参加して、3日間にわたって行われた各セッションでは数多くの名言が飛び出しました。
そこで今回は、各セッションで飛び交った名言の中から、いくつかピックアップしてご紹介します。
(※)P&G出身でマーケティング分野で目覚ましい業績を上げているエリート集団を指す表現。
名前を覚えてもらうのが、「認知」ではない。
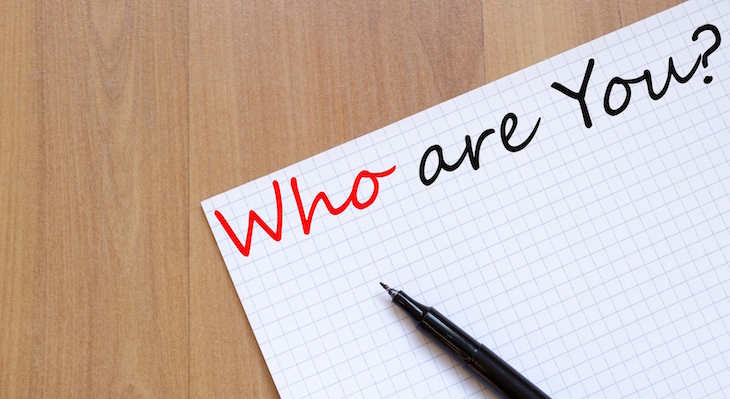
初日の基調講演では、ファブリーズと消臭力が繰り広げてきた熾烈な競争の裏側について、それぞれのマーケティング責任者たちが語るトークセッションが行われました。
多くの”マフィア”と呼ばれる優秀なマーケターを排出しているP&Gと、先行企業とはいえ予算規模やリソースでは劣るというエステーの壮絶な頭脳戦。
しかし、その裏側でいえば、お互いの思考に大きなちがいはないようで、「消費者の好きをどうつくるか」「どう恋に落ちてもらうのか」を考えているのだとか。
そんな話の流れで飛び出したのが、「名前を覚えてもらうのが、認知ではない」というコメント。
では、一体何をもって認知というのでしょうか?
「名前だけでなく、どういう人かを覚えてもらって初めて”認知”といえる」。これが、ステージ上のトップマーケターの共通見解でした。
「好きをつくる」「恋に落ちてもらう」のに、名前を覚えてもらうだけでは不十分。「どういう人か」覚えてもらって、ようやくスタートラインに立てるといえます。
それでもまだ「好きになってもらえる」確率は10%くらい。
「残りの9割をどうするか」がマーケターにとって大きな壁として立ちはだかるのですが、スタートとして重要となるのが、「どういう人かまで認知されること」というわけです。
しかしそう考えると、コンテンツマーケティングは「認知」を生み出すうえでは結構有用な手法といえそう…と、これを語り始めると長くなるので、また別の機会に。
競合他社を意識しすぎない。

話はかわって元セブン&アイHDでオムニチャネル戦略の指揮を執ったCIO、鈴木氏を招いて行われた、2日目の基調講演。
セブン&アイの強さの秘密、オムニセブン(セブン&アイHDのオムニチャネル施策)とは本来どういう概念で組み立てられていたのか、など小売・流通の世界を取り巻く深い話が展開されました。
特に興味深かったのは、鈴木氏が在籍していた当時、セブン&アイHDのトップは社員がマーケットリサーチと称して、他社の店舗を見に行くことを禁止していたことがあるそうです。
理由は2つあって、1つめは、横を見ずに、ひたすら目の前の顧客ニーズと向き合うことで他社と競争することなく「自分たちの土俵」でお客様と向き合うため。
2つめは、もはや競争は1つの業界や業態のなかだけでなく、まったく異業種から競争相手が現れ、出自の異なる企業や商品、サービスが競い合う時代になっているからだといいます。
そして、このとき重要なのが「お客様のため」ではなく、「お客様の立場で」発想をすることだと指摘しています。
顧客ニーズに答えなければいけないというのはだれもが言葉では理解していますが、「お客様のために」という発想をすると過去の経験に縛られた思い込みになる、またどこかで売り手都合が優先されていることが多くなります。
一方「お客様の立場で」考えると、自分たちに不都合なことでも実行しなければいけないからフラットに発想できるといいます。
マーケターというのは、あたりまえのように競合を設定して分析し「競合に対する自社の優位性をいかに築き、強化するか」を考えがちではないでしょうか。
しかし、イノベーションを起こそう!とか、市場を新たに創造し開拓しよう!という状況においては、この「あたりまえのようにする競合分析」が邪魔をすることもあるのかもしれません。
そもそも「あたりまえ」と思っていることも、ひょっとすると「邪魔」になるかもしれない。そう考えると、もっと頭を柔らかくせねば、と実感させられました。
社会課題に向き合う

「このプロダクトには、命がかかっている」。ふつうに仕事しているなかでは、そうそう言わないし聞かないであろうこのセリフが飛び出したのは、3日目の基調講演。
このセッションでは、世界最大級の広告賞「カンヌライオンズ」のモバイル部門グランプリを受賞した、リクルートライフスタイルの精子チェックサービス「Seem」開発メンバーが、開発の裏側について語りました。
Seemは、少子化という社会課題に向き合うプロダクトとして開発をスタートしており、6組に1組のカップルが悩まされているといわれる「不妊」に対する男性側の意識と行動を変化することをめざしています。
不妊の原因の約半数は男性が関係するといわれています。にも関わらず日本は諸外国と比べて男性が体裁にこだわる傾向が強く、妊活への男性の参加が遅れることにより、貴重な時間やお金が浪費されてしまいがちだそうです。
晩婚化・晩産化が進んでいることも相まって、子どもが欲しいと願い妊活するものの、結果的には子どもをもうけられないカップルも見られ、そのことが少子化の一因とも考えられているのです。
実際、社内ユーザーでのテスト時に精子に異常があることが判明した夫婦は、早期の対応を進めた結果、子宝に恵まれたのだとか。
カンヌでも高く評価されたという少子化、また不妊という社会課題に対して「命がかかっている」と考え、真摯に取り組んだSeemのアプローチは、まさにこれからのマーケティングのあるべき姿といえるでしょう。
感情に引っかかる。

「ヘーホンホヘホハイ」。みなさんは、食べたことがあるでしょうか?
2017年10月に行われたマクドナルドのキャンペーンでは、「ヘーホンホヘホハイ」という謎の(?)商品が話題となりました。
ついに正解発表👏です!10/4(水)から期間限定発売🎊のベーコンとポテトたっぷり、ほっくほくでクリーミーな #あのパイの商品名 は、#ヘーホンホヘホハイ✨!RTすると抽選で100名様に『フハホケース』がその場で当たる🎯 https://t.co/3sWqCGVta7 pic.twitter.com/b3UxBqHnCv
— マクドナルド (@McDonaldsJapan) October 2, 2017
「ヘーホンホヘホハイ」をはじめ、次々と話題となるキャンペーンでV字回復を遂げたマクドナルドのCMO、足立氏が3日間の最後のセッションで述べたのが「しょうもないことでも、エクストリームさせてやりきれば、感情に引っかかる」という点。
「ヘーホンホヘホハイ」でいうと、「ベーコンポテトパイ」をハフハフしながら言ったらそうなる、というだけのしょうもない話とも捉えられます。
実際、最初に見聞きした時に「なんじゃそりゃ?」と思った人も多いのではないでしょうか。
しかし、メニューやパッケージに至るまでそれをやりきると、感情に引っかかり、話題になり、キャンペーンとして成功する、というわけです。
消費者の立場からいえば、「なんじゃそりゃ?」と思わされた時点で、キャンペーンに巻き込まれているともいえます。
まずはアイディアを集め、一見しょうもないと思える場合でも、それを否定せずエクストリームさせて考えてみること。
その日々の積み重ねが、プロモーションやマーケティングの成功につながっていくのだ、と気付かされる一幕でした。
今日の必勝法は、明日の必勝法じゃない。

同じ最後のセッションで、「王様ゲームが合コンの必勝法ではなくなった」ことを例にあげながら、「今日の必勝法は明日の必勝法じゃないと考えて取り組んでいる」と語ったのは、ドミノ・ピザCMOの富永氏。
マーケティングに限らず、ビジネスにおいてよく出てくる「昨年は何やったっけ?」とか「前にこれやって成功しているからまたやってみれば」という話。
一見、論理的にも見えますが、世の中も人も激しく変化しつづけるこの時代に、本当にそれで通用するのかどうか、ただ楽をしようとしているだけではないのか、きちんと考えてみることが必要です。
吉野家のCMO、田中氏も同調し「20世紀のプロデューサーがダメだと言うことを、21世紀にやると成功した」と自身の経験について語りました。
すでに多くの成功を経験してきているトップマーケターがトップマーケターとして成果をあげつづけているのは、過去の成功体験や自分の固定観念にとらわれないスタンスあってこそ、なのでしょう。
「今日の必勝法は明日の必勝法じゃない」と考え、慢心せず、成功するためにアイディアを探し続けること。心がけていきたいものです。
見えないものを見る力

ここまでご紹介した以外にも、名言・名エピソードが数多く飛び交ったマーケティングアジェンダ2018。
その全体テーマは、「Create The Future ~ The Power of seeing the invisible ~(未来創造:見えないものを見る力)」というものでした。
現状の分析や対応だけでなく、未来を予想し、想像し、先回りして市場を創造していくことが、マーケターにますます求められる時代。
「見えないものを見る力」。マーケティングの極意は、ここにあるのかもしれません。